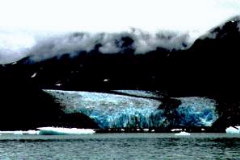 マクブリッジ氷河
マクブリッジ氷河
深いグレイシアー・ブルーに吸い込まれそうだ。
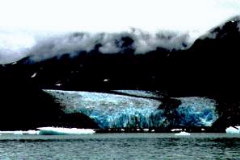 マクブリッジ氷河
マクブリッジ氷河
深いグレイシアー・ブルーに吸い込まれそうだ。
7日目。雨が降り続いている。シュラフも衣服もすべて濡れていた。寒い。とてもテントから出る気がしない。午前中にトレッキング、さらに奥のミュアー・グレイシアーへの旅を計画していたが、震えながら濡れたシュラフにくるまったままだった。自分の体温で暖かくなったぬるま湯のような場所からなかなか抜け出すことができなかった。
星野道夫の「イニュイック(生命)」を読む。マクブリッジ・グレイシアーの崩壊する音が遠くから断続的に聞こえてきた。星野さんの言葉とアラスカの大自然、そして雨が僕を濡らしていく。
暖かい飲み物を作りに思い切ってテントから這い出し、クッキングサイトへ。霧雨と湿った雨が僕を包む。MSRはすぐに心地よい音を立てはじめた。暖かく湯気を立てるお湯に、アールグレイのテイーバックをほうり込んで、カップを両手で包む。香りがつかの間の幸福をプレゼントしてくれる。そのままクリークをゆっくり歩いて戻ると、群生するヤナギランの手前にムースの骨があった。雄々しい雄の角も、何個所か欠けていて物悲しい。ひっそりと転がる骨を見ながら、ムースの最後の瞬間に想いを馳せる。二つの巨大なグレイシアに囲まれた場所に、どうやってやってきて、死を迎えたのか。
再び氷河が崩壊する轟音。
沈降していた気持ちが活発になってきた。動こう。雨の世界でも、こんなにいろんな事に出会える。生き物たちもこの雨の中でそれぞれの生を営んでいるに違いないのだ。すべて濡れたままパッキングを完了させ、暗い水面へと漕ぎ出した。
やってきた時よりもさらに多数の氷塊が海面を埋め尽くしていた。その先には霧に霞む氷の牙、マクブリッジ・グレイシアーが見えてくる。深く吸い込まれそうなグレイシアー・ブルー。吸い寄せられそうだ。慎重に氷山を避けながら進む。鋭利か氷で船体を裂かれてはたまらない。しかし、氷河の魔力には勝てず、引き込まれる様に氷河へ向かってしまった。
氷山にたたずむカモメたち。冷たくないのだろうか。
手はもう感覚がないほど冷たい。
お尻も痛いぐらいに冷たかった。このままで霜焼けでころではすまないかもしれない。
ふと前方に目をやると、大きな塊が氷のオブジェに止っていた。猛禽。
一羽の巨大な鷹だった。Hawk。インディアンの言葉で“魂”の象徴とされる。
初めて、僕が憧れのユーコン川を下った時、たき火をしていると鷹がテントに止ったことがある。ほんの数メートル離れて、長い間そこにいたのを覚えている。
その川旅で一番心に残る出来事だった。同じ年の同じころに、星野道夫氏がカムチャッカで熊に襲われこの世から去ってしまった。アラスカの知人たちへ別れを告げに行く途中で羽休めに僕の所へ訪れてくれたのかもしれない。
そんな風に勝手に思い込んだものだ。
だから白頭鷲と比べると地味な存在にされがちだが、鷹は僕にとって特別な意味を持つ。おりしも僕の大好きな九州の川辺川のダムの審議をめぐって大きく動こうとしている時、熊鷹が川辺川を守ってくれるのではないか、そんな期待を抱いていた時だった。
目の前の鷹は微動だにしない。氷山の上でまるで凍り付いたかのようだった。
まるで今の僕の姿を象徴するかのように。
スピリッツァル…魂の熱い叫び。情熱や勢いは僕の代名詞だった。
自分に自身を持ち、周りの事を気にせず走っていたあの頃…
しかし、今の自分ときたら、冷え込んで行く氷のようだ。
やさしくなった。丸くなったと人は言う。
しかし、僕は望むものを手に入れたのだろうか。
想うとおりの姿に近づいたのだろうか。
冷たい氷の海でいろんなものが凍てついてしまったようだ。
近づきすぎてしまった僕に、気づいてようやく鷹は飛翔に移った。
視界から消えるまでその姿を目で追った。
ふと気づくとすっかり氷山の群れに囲まれていた。氷山どうしがくっついて、道をふさぎはじめる。どうやら潮が変わったらしい。パドルで氷を押しやって隙間を作りながらようやく抜け出る事ができた。
霧雨の中を南下。Goose Coveを回り込むころには、完全な向かい風となった。
ブレイクした波が次々にバウに向かって飛んでくる。
力尽きるまで漕ぐ。もうダメだ。上陸。なんと往路で上陸した場所だった。
日課の重労働の荷揚げをしたあと、手早く食料を胃に収めて、テントへ逃げ込んだ。
クタクタだった。深い疲労感と湿気につつまれ、泥の様に眠った。