Introduction of Manichaean Religion

マニ教概説・序説
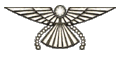 |
 マニ教とは マニ教とは 
マニ教(Manichaeism)とは、西暦3世紀半ば、ササン朝ペルシア帝国治下のイランで、マニ(Mani, Manichaeus)によって創始された啓示宗教である。古代ユーラシアの世界宗教の一つで、民族・言語・文化・国境を越えて、イベリア半島から、東はインド・西域を越えて中国にまで布教され、広く信者を得た「普遍宗教」であった。歴史のなかで、マニ教はいつしか淘汰され消え去ってしまったが、今日にも残存していれば、その教えの普遍性から云って、仏教、キリスト教、イスラム教と並ぶ、第四の「世界宗教」でもあった。
マニ教の創始者マニは高貴な出自であると伝えられている。彼の父と母は、ササン朝に先立つアルサケス朝ペルシア(パルティア)の王族に連なる家系出身であったとされる。しかしこれは、マニ教信徒のあいだで生み出された後世の潤色であろう。マニは、西暦216年4月14日(太陰暦のニサンの月8日)、南バビロニアのユーフラテス川沿いの小村マールディーヌで生まれた。240年、マニが24歳のとき、聖なる天使パラクレートス(アル・タウム)の啓示と召命を受け、マニ教を宣明する。(マニの誕生と天啓についての詳細は、本サイトの「マニ教概説第一章」の第一節・第二節を参照)。 マニの生涯は、ほとんど福音伝道の放浪の旅に費やされたが、その伝道の初期、ササン朝第二代の王であったシャープール一世の弟がマニ教に帰依し、この弟の仲介でマニはシャープール一世に拝謁し、ペルシア帝国内でのマニ教布教の許可を王から得る。マニは、マニ教の教義綱要をみずから著した最初の教典『シャープーラカーン』を王に献げる。これに続いてマニは、数多くのマニ教教典を著すが、その大部分は散逸し今日残っていない。マニは大宗教の開祖であって、かつみずから教典を著した最初の人物としてユニークであるだけでなく、芸術的才能に恵まれ、彩色画集の教典をも著した。その結果、マニは若い頃、絵師としての訓練を受けたという伝承も生まれた。 シャープール一世の庇護の元、マニはマニ教をササン朝ペルシアに広く布教し、更に弟子たちを派遣して、シリア、エジプト、インドなどにもマニ教の勢力を拡大させる。しかしイランにおけるマニの立場は、庇護者であったシャープールの没後、急速に悪化し、シャープールの継承者であるバハラーム一世はマニを断罪し、マニは捕らえられ殉教する。西暦276年前後のことであった。(シャープール一世はマニ教に帰依していた訳ではなく、マニの医療技術を評価していたと云われる。シャープール治下、祭司の長モーバドのキルディールを中心に、ゾロアスター教の国教化がまた同時に進められていたのである)。マニの殉教については、マニ教内部で伝承が作成され、様々な残酷な受難をマニは被ったとも伝えられて来たが、近年の資料からは、マニは比較的穏やかな状況で獄死したものと考えられる。 マニは生前、殉教を予見し覚悟しており、マニ教の教団組織を編成していた。しかしイランすなわちササン朝ペルシアにおいては、ゾロアスター教が民族宗教として国教となり、マニ教を弾圧したため(マニの後継者である初代教長スィスィンも殉教したとされる)、マニ教は、東方インド、更に西域へとその勢力圏を拡大させた。また西方では、ローマ帝国領で広く布教され、原始キリスト教に匹敵する宗教勢力となった。シリア、パレスティナ、エジプト、北アフリカには多数のマニ教信徒やその共同体が生まれ、初期キリスト教最大のラテン教父であるヒッポの聖アウグスティヌスもまた、若き頃、マニ教の教義に牽かれ、「聴講者」として信徒に加わっていた。 しかし、キリスト教がローマ帝国の国教の地位を占め、度重なる公会議開催を通じて、内的な異端論争を行うにつれ、異教であるマニ教もまた「グノーシス主義異端」の一派として迫害され、紀元4世紀から5世紀を最盛期として、西方におけるマニ教は次第に衰退して行った。またメソポタミアでは、7世紀にムハンマドを開祖としてイスラーム教が成立し、ササン朝ペルシアを滅ぼすが、イスラームもまたマニ教を「異端異教」として迫害したため、マニ教はその本拠を次第に東方へと移して行った。 西暦694年に、マニ教の布教者が当時全権を掌握していた唐の武則天
 神話と教義 神話と教義 
マニ教は、宗教としてその形態を判断するなら、典型的な「混淆宗教(シュンクレティズム)」で、ゾロアスター教、ユダヤ教、キリスト教、仏教などの教義や神話などが、一見したところ脈絡なく、荒唐無稽なばかりに接ぎ木され混成されているようにも見える。
この一つの理由は、宗祖マニが、「教えの神髄」の福音伝道を重視し、みずから書き著した教典を諸国語に翻訳させるにおいて、入信者が理解し易いように、ゾロアスター教の優勢な地域への伝道のためには、ゾロアスター教の神々の名や神話を適用し、キリスト教・ユダヤ教が優勢な地域への伝道のためには、それぞれユダヤ教やキリスト教の神話や教義に仮託してマニ教の教えを説くことを許容したためであろう。むしろ開祖みずから積極的に推奨したため、教典の翻訳や新教典の作成などが重なるにつれ、次第に、本来のマニ教教義が、見かけ上錯綜したものとなり、混同や誤解を招くような形になって来たと考えられる。 また、マニやマニ教徒がこのような方針を取ったのは、本サイトの「グノーシス主義基本用語集」の「マニ教」の項目でも述べているように、マニ教は何よりも「グノーシスの宗教」であり、その「基本的な教え」は、グノーシス的現存在姿勢から導かれていたためであるとも言える。様々な宗教の神の名や神話要素を、適合する形でマニ教神話に取り込み、「マニ教グノーシス主義神話」を構成するのがその特徴であるためである。 マニ教は、グノーシス主義の反宇宙的二元論を前提にし、「光・霊・善」と「闇・物質=肉・悪」の二元論より成る。イラン型グノーシス主義の特徴として、これら二つの原理が、世界には原初のときより、並列して存在していたと教える。
このようにして存在する我々人間は、闇の物質で造られた世界に生き、我々自身の肉体もまた闇の物質である。しかしアダムとヘーヴァを通じて、またセトを通じて、我々の内部には「光の元素の破片」がひそんでいる。この闇の世界から救済されるためには、我々は、「グノーシス」すなわちマニ教の啓示を知り、真実に覚醒し、内部の光の元素をまず月に、それから太陽へと帰還させ、最終的に「光の王国」へと戻さねばならない。
マニ教徒は、グノーシス(智慧)を知り、闇のアルコーンの策略である「生殖行為」を避けねばならない。また光の元素を少量とは云え内に含む、人間以外の動物や植物を無用に害したり殺すことを止め、人間や生物の内部に隠されている「光の元素」を純粋に抽出して、光の王国への帰還を促進させねばならない。やがて、光と闇のあいだで「最終戦争」が起こり、物質の世界は滅び、光と闇の二つの原理は、完全に分離され、再び混じり合うことはない。これがマニ教の神話であり宇宙論であり、救済論、そして教義である。  信徒と信仰生活 信徒と信仰生活 
西方グノーシス主義(シリア・エジプト型グノーシス主義)は、生殖行為を絶対的に禁止したため、世俗的一般大衆への布教という観点から見れば、理念的で、永続しない教えであり、また知的選良だけに開かれた宗教だとも言える。これに対し、イラン型グノーシス主義の最高形態であるマニ教の信徒論は、おそらく仏教の出家信徒集団と在家信徒集団の二分構造から着想を得たのか、信徒を、厳格なマニ教の戒律に従い修行する「選良者」集団と、緩やかな戒律のもと世俗生活を送りつつ、選良者たちの生活を支える「聴講者」集団の二重構造とすることで、「世代に渡り持続するグノーシス主義宗教」を実現した。
宗祖マニは、預言者であり使徒であったが、同時に巧みな教団組織者であり、彼はマニ教の教義と神話を「福音書・教典」を著すことで明らかにしつつ、同時に、増大する信徒の数に応じて、その共同体を律する組織編成原理をもみずから構築した。「選良者」と「聴講者」の関係は、キリスト教の「修道士」と「平信徒」の関係に似ているとも言えるが、根本的に異なるのは、キリスト教の修道士は、みずからの修道共同体のなかで、生産活動を行い自給自足したという点である。マニ教の「選良者=修道士」は、その宗教の本来の教えの通り、生殖行為を行なわず、かつ物質的生産活動を一切行わないという原則で律せられていた。 マニ教の選良者(完全者)=修道士は、仏教の出家僧と同様、物質的生産活動には従事せず、従って彼らが生存を続けるに必要な一切の物資は、在家信徒である聴講者からの「布施」によってまかなわれていた。マニ教の修道院は、キリスト教のそれと似て、様々な精神活動・信仰生活のための施設を備えていたが、農業・畜産を含め、生産のための施設、また例えば食料貯蔵庫の役割をする倉庫などは備えなかった。衣食住のための物資的基盤は、在家信者である聴講者が、日毎に修道士に布施を通じて提供したのである。 マニ教の選良者と聴講者は、一方は霊的な修行に励み霊的慰めを聴講者やその他この世の人々・生命にもたらすことを使命として他方と区別された。選良者は男女共に、「白い衣服」をまとい、それ故、マニ教徒は「白装束」とも呼称された。マニ教の聖職者階級は、選良者のなかから選ばれ、マニの後継者と見做される「教長」を頂点に、その下に、三段階の聖職者組織があった。最上位には、キリストの十二使徒に倣った十二人の「教師」がおり、更にその下に、七十二人の「司教」、その下に三百六十人の「管理者」がいて、マニ教教団の組織運営や布教に当たった。これ以下の一般修道士は男女共になれたが、上級聖職者であり定員の定まっている以上の三段階の聖職者職は、教長も含めて男性だけがなれた。 マニ教信徒には当然のことながら「戒律」が定められていたが、それは目的とするものは同じでも、選良者と聴講者ではおのずから異なるものであった。無論、前者の戒律はきわめて厳しかった。しかし、選良者たちは、この厳格な戒律を喜びを持って遵守したのだということも重要である。修道士に課された五つの戒律は:
修道士つまり選良者の義務は、宗祖マニに倣って、世界中を放浪し真理の福音を伝道して行くことにあった。従って、修道士は定住者ではなく、仮に一箇所に長く住んでいたとしても、神または上長の命令があれば、ただちにどこへでも伝道の旅に赴く必要があった。それに対し一般信徒つまり「聴講者」は、通常は定住者であり、結婚し、家族と共に生産活動に従事して暮らすのが普通であった。しかしこの二つの信徒の区別は、相互補完的であり、一方が他方に対し絶対的に優越するというような関係ではなかった。それぞれは、光の救済というマニ教の使命において、異なる役割を果たしたのである。
一般信徒つまり聴講者の守るべき信徒義務行為は五つに分かれていた。これはイスラーム教の「五柱」つまり「信仰告白・祈祷・喜捨(ザカート)・断食・巡礼」と極めて類似しているが、マニの称号「預言者の印璽」を、ムハンマドもまた名乗ったように、本来、マニ教の宗教体系よりイスラーム教が模倣し受け継いだものである。マニ教聴講者の五つの義務は:
マニ教の祭礼や祭日は、キリスト教より導入されたものを含め、複数があったが、なかでも、もっとも重要なのは、「ベーマ祭」の典礼であった。ベーマとはギリシア語で「座」を意味し、ベーマ祭礼のときには、誰も座ることのない椅子の座が準備された。ベーマ祭礼は、春分とマニの殉教を記念し、祭礼の最後の日は、マニの魂がこの世界から離れ、光の国へと昇天して行った日に当たっていた。準備された空のベーマ(座)には、この日、マニの霊が宿ると信じられた。
 マニ教の終焉と位置付け マニ教の終焉と位置付け 
マニ教はすでに述べたように、グノーシス主義宗教であり、東方型(イラン型)グノーシス主義の典型的世界宗教であった(「イラン型」「シリア・エジプト型」という区別や、「グノーシス主義」の概念については、本サイトの「グノーシス主義基本用語集」の「ヘレニク・グノーシス主義」の項目を参照)。マニ教グノーシス主義は、世俗的生活を行い、生産活動や生殖行為も行う「聴講者」信徒のクラスと、専らマニ教の宇宙観・救済論に従い、霊的生活に専念した「選良者」信徒のクラスの二つの集団で教団を構成することにより、互いに補完的な構造を造ることで、永続する宗教共同体を構築することに成功した。
とはいえ、マニ教はあくまで「グノーシス主義宗教」であり、その基本的な救済のヴィジョンは、グノーシス主義研究者ハンス・ヨナスが提唱した「現存在の姿勢( Daseinshaltung )」にあった。非グノーシス主義宗教一般では、その「信仰神話」は、具象的な神の名称や、登場者の固有名などが、その宗教に特定して、固有の意味と形式を備えるのが普通である。「共通の信仰神話」とその「解釈コード」を共有することが、「同じ宗教の信徒」であることの確認であり、特定宗教の信徒の「アイデンティティ」の保証となっている。 しかしグノーシス主義宗教の場合は、「信仰神話」に基づいて、共有の「共通信仰」が保証されるのではなく、共有するのは、その「固有のときと状況の現存在姿勢」であり、この共通性において、「同じ宗教の信徒」であるという自己の本来的保証が確信されるのであり、マニが自己の著した複数の福音書を多数の異国の言葉に翻訳するとき、相当に自由な意訳を認めたこと、または、積極的に「意訳」「翻案」を推奨したことは、マニにとっても、その信徒にとっても、重要であったのは「現存在姿勢の了解」であって、「表層的教義」や「宗教神話」は二次的に援用する対象だったからである。 マニ教の神話や教義には、ゾロアスター教の神々の名も出てくれば、ユダヤ教の神や神話的人物、キリスト教の天使・使徒なども登場し、更にギリシア神話の神々や英雄、ペルシア神話、インド神話の神々、中国に入って後は、道教の神々やその宗教用語等も援用されている。近年、トゥルファンや敦煌、高昌などで発見されている西域の言語や中国語で記されたマニ教教典が、聖アウグスティヌスの反駁書に引用されているマニ教の教典や、あるいはイスラームの記録者(例えば、イブン・アル・ナディーム)の伝えていることと比較すると、著しく内容が異なるということからも、時代と共に、マニ教の教義が変化して行ったのか、または先に述べたように、グノーシス主義宗教の固有の特徴として、「教えの神髄」は、外的な構成神話の内容にではなく、「反世界的な二元論」と「救済されるべき光の霊」そして「救済者の啓示」という、グノーシスの構成要素こそが本質だということかも知れない。 マニ教は、どの宗教と出逢っても、相手の宗教が神聖なものとして崇敬・保留する神の名や、信仰神話を勝手に内部に取り入れて、独自の解釈と意味付けを与えるというグノーシス主義宗教の特徴を遺憾なく発揮している。そのため、成立の故地イランにおいては、民族宗教ゾロアスター教の「異端」として迫害され、地中海世界では、キリスト教の「異端」として、これも迫害された。七世紀にイスラーム教が成立して後は、マニ教が教化した広大な地域に、マニ教の伝統を逆に利用してイスラームの布教が行われたというのが、より事実に近いにも拘わらず、イスラーム教側からも「異端」の誹りを受ける。ヒンドゥー教からも仏教からも「異端」とされた。これらは、マニ教が他のグノーシス主義宗教と同様に、既存の宗教や哲学の用語・固有名・概念を援用して、その「創作神話」を構成するという処からおそらく来ている。 このように古くからある宗教からも、新しく興った宗教からも、様々な意味で「異端」とされたマニ教は、それでもユーラシア大陸の世界宗教として、マニの時代から千年以上存続する。イランにおいて迫害を受けたマニ教であるが、しかし、マニが定めた教会組織の中心部である「教長」の座するマニ教の本拠は、ササン朝ペルシア時代を通じてバビロニアに置かれていた。ササン朝ペルシアの方針として、マニ教徒に対する国内移動を制限したため、バビロニアから移動できないまま、この地域に本拠を置いたともされる。 6世紀末から8世紀にかけて、バビロニアのマニ教本部は、オクソス川東方のサマルカンドの分離運動に直面し、更に続けては、バビロニアの本拠そのもので指導権をめぐって内紛が起こる。イスラーム教がアラビア半島で勃興し、またたくあいだにササン朝ペルシアを滅ぼし、東はインドの西端から西はイベリア半島まで、広大なイスラーム帝国を築いた。8世紀後半には、ウマイヤ朝を倒したアッバース朝三代目カリフ、アル・マフディーがマニ教を「異端」と断罪し弾圧を始める。やがて、西暦十世紀には、バビロニアの教長はサマルカンドに移動し、このとき、マニ自筆の教典写本なども喪失されたようである。 マニ教は、イスラーム教に背後から追撃を受けるように、東へ東へと移動して行った。中国において8世紀に伝道に成功し、ウイグル汗の改宗でやがてウイグルの国教となったのも束の間、ウイグルはキルギスに敗北し、9世紀には、中国においてマニ教を含めて諸外来宗教の迫害が起こる。中央アジアにおいて、マニ教は、ウイグルの首都高昌(ホッチョ)や、サマルカンド、トゥルファンなどの砂漠のオアシス都市に細々と存続するが、十三世紀頃には、中央アジアからはマニ教の痕跡は消えてしまった。ウイグルはイスラーム教に改宗し、中国における「ウイグル」の漢字音訳の「回鶻」を取って、イスラーム教を、中国では「回鶻教」つまり「回教」と呼称した。 西暦3世紀後半のディオクレティアヌス帝の迫害も乗り越えて、4世紀から5世紀にアレクサンドリアで最盛期を迎えた西方のマニ教も、ビザンティン帝国とローマ・カトリック教会双方から迫害を受け、6世紀から7世紀頃には姿を消す。しかし「マニ教的伝統」は西洋に長く残り、東方アルメニアのパウロ派や、ブルガリアで10世紀から12世紀にかけて繁栄したボゴミール派、更に南フランスのラングドック地方で、13世紀頃まで栄えたカタリ派などが存在し、「正統教会」から「マニ教的異端」の烙印を押され弾圧され、滅ぼされる。 マニ教の最後の痕跡は、9世紀の中国における「会昌の禁圧」を辛うじて逃れたマニ教宣教師が、福建の泉州で「秘密結社」の形でマニ教会を保存したことだと云われている。しかし、泉州のマニ教は、身の安全のためか、道教と混淆した形となり、十五世紀を最後として、マニ教としては確認できなくなった。 西方のパウロ派やボゴミール派、カタリ派などは、「マニ教的異端」ではあっても、教祖としてマニを承認しないので、これらはマニ教の影響を受けた「二元論的グノーシス主義宗教」の諸派ではあっても、マニ教の分派ではないということになる。 かつては、広大なユーラシア大陸の東西の端にまで信徒が広がっていたマニ教、イスラーム教布教の下地を事実上造ったと言える「平和の宗教」マニ教が何故世界史の舞台から消え去ってしまったのか、それを謎と云えば謎かも知れない。しかしキリスト教の異端論争の歴史を顧りみれば明らかなように、宗教はときの政治権力者にいかに受容されるかが、その存続・繁栄の成否を決めるのだとも言える。マニを庇護したシャープール一世はマニ教の信徒ではなく、ゾロアスター教徒であったことを考えれば、マニ教は、世界史のなかで、敗北すべくして敗北したのだとも言える。 消え去ったことで、マニ教は、純粋な平和の宗教であったことを、歴史のなかで証明しているのだとも私たちは思惟する。  参考文献 参考文献 
Noice et Marie RA. 2004:0728
|